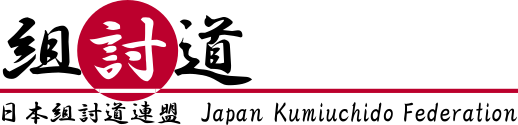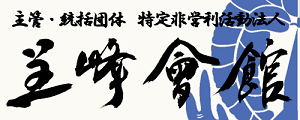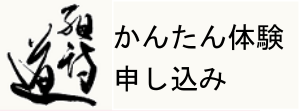お知らせ
2024/01/07 活動内容を更新しました。
2021/10/26 オンライン稽古をスタートしました。体験希望の方はこちら
2021/10/26 ホームページリニューアルしました。
2020/05/05 緊急事態宣言を受けた組討道連盟での対応について
組討道とは
「組討道」は
「空手道」の突きや蹴りを主体とし
「銃剣道」で行われている短剣道の武器で突く技法
「剣道」で行われている小太刀の武器で叩く技法
「柔道」「少林寺」「合気道」で行われている相手を投げる技法
それら全てを総合的に修得でき、
制圧・確保を最終目標とした「武道」であり護身術です。
お問い合わせ
組討道連盟事務局 電話番号 052-883-0333
お問い合わせ時間 月曜日~日曜日 10:00~22:00
*お休みはありません。お気軽にお問い合わせ下さい。